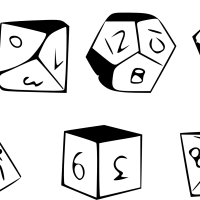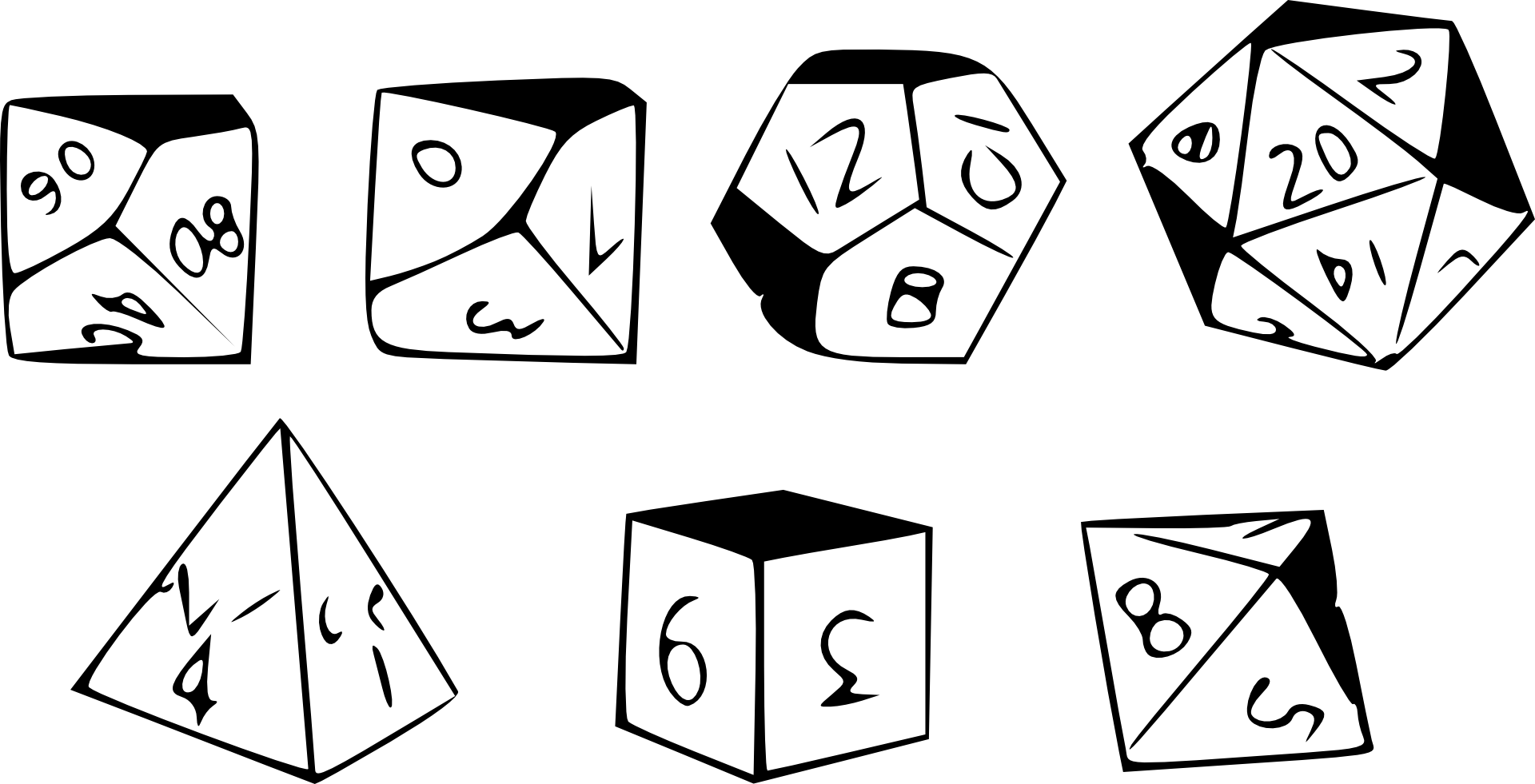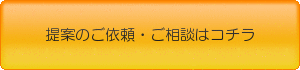2015年12月に50人以上の規模の事業場に義務付けられたストレスチェック制度。
お勤めの事業場で受検された方もおらっしゃるかと思います。
先日、お伺いしていた事業場でこんなお話がありました。
その事業場は会社全体では50人以上の規模がありますが、単体では50人を少し下回っています。
つまり今回導入されたストレスチェック制度の実施義務のある対象事業場ではありません。
ただ、どのようなものかと実際に厚労省版のアプリをダウンロードして数人でチェックをされてみたそうです。
人事労務のご担当者さまの感想は、「ストレスが高いと出ても、医師との面接対象者となり、本人から面接の申し出がなければ事業場は何もすることができない。今後実施するのであれば、集団分析をするようにしたい。」というものでした。
可能な範囲で事業場からの何らかのアクションを取りたいと考えておられるご担当者さまの考えをうれしく思いました。
目次
改めてストレスチェック制度の目的を考えてみる
ストレスチェック制度の目的は、主に一次予防「本人のストレスへの気づきと対処の支援及び職場環境の改善」です。
集団分析は努力義務ですので、それをしなければ「本人のストレスへの気づき」を促して終わり。という事業場も、導入初年度の今年は多かったように思います。
さて、来年度からどうしましょう。
ストレスへの気づきに終わらない、「対処」への支援
その中で、「本人のストレスへの気づき」で終わらず、面接対象者がいたが希望者がいなかったということから「ストレスへの対処の支援」を検討された事業場もあります。
具体的には、ストレスコーピング(ストレス対処法)についての研修をさせていただきました。
日々、様々なストレスを受けていますが、物事のとらえ方一つ、受け流し方一つ、ものの伝え方一つで、周囲との摩擦が大きくしてしまったり、小さくできたりします。
ストレスに対して、裸一貫で勝負するよりも、何かしらの武器をもっておくことで、対処の方法も変わってきます。
コミュニケーション手法を複数知り、適切な対処ができれば、ストレスを増幅させることも少なくなります。
義務化されたストレスチェック制度を「手間とコストがかかるだけ」のものにするのか、かけた労力以上の効果が生まれるかは、その後の取り組み次第です。
集団分析結果をどう活かせばよいか分からない
集団分析をされた事業場にもサポートに伺いましたが、多くの事業場のご担当者さまが、結果をみて「はて、これをみてどうしましょう。」とお困りでした。
何とかその結果を活かす方法を考えることも大切ですが、集団分析結果は、あくまでも一つの見方です。
円柱があるとしたら、集団分析の結果は真上からみた円形でしかないかもしれません。横から見れば長方形で、様々な角度から総合的に見て円柱に見えます。
厚労省版のアプリで集団分析を出しておられる場合、平均値を出しているので、高ストレスの集団と低ストレスの集団が同数分布していたとしても平均値としては、丁度よいといった結果が出ているというパターンもないとは言えません。
この集団分析を他の角度から見る方法として、組織で最も多く出現した評価(最頻値)や評価点を多い順または少ない順に並べたときに中央にある点数(中央値)を適宜組み合わせてみることも方法の一つです。
例えば、最頻値や中央値と比較し、平均値が小さい場合は、少数の人が極端に低い数値になっていることが考えられます。
このような方法もありますが、別の角度からみるためにはストレスチェックのみでの対処には限界があります。
「4つのケア」を機能させるにはどのようにすればよいか?という視点
例えば、仕事が量的に多いという結果が出たとしても、多いと感じている原因に何らかのボトルネックが作用している場合であれば、実際の人員に対しての業務量は多くないかもしれません。
何がボトルネックとなっているのかをヒアリングすることなく、単純に業務量を減らしても解決には結びつかないかもしれないということです。
集団分析の結果は、従業員へのヒアリングのための切り口の一つにはなるかもしれません。ヒアリングの他には職場環境改善に向けた小集団活動も効果的です。
何より大切なことは出てきた問題だけに対処するモグラたたきにならないように、事業場で「4つのケア」を進めていくということです。
セルフケア、ラインによるケア、事業所内産業保健スタッフによるケア、事業場外資源によるケア、メンタルへヘルス対策におけるこれら4つのケアを機能させるための方法を考え、その中のストレスチェックの位置づけを改めて考えていただきたいと思います。
具体的に「こうしたい」ということがご不明であっても、まずは現状をお聞かせください。御社にあった方法をご提案できるかと思います。
具体的にどうすでばよいかわからないなど、お困りのことがございましたら、お気軽にお問い合わせください。