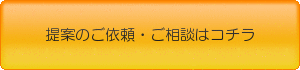「地元で採用ができなくなってね。今は四国行脚しているよ。」
製造業の人事労務のご担当者様からこのような言葉をよく耳にするようになりました。
今の採用難は、序の口。これから労働人口が減る一方です。
今何らかの手を打っておかなければ、身動きが取れなくなってしまう時代がもうすぐそこまで来ています。
今日は求職者への「会社の見せ方」を考えてみたいと思います。
目次
求職者は求人募集欄のどこをみる?
「この人を採用したら・・・」
採用担当者が、求職者をみて、御社で働いている具体的なイメージが浮かんでいれば、その方は採用になっているでしょう。
「・・・」の部分に具体的なイメージが言語化されているということです。
逆に、会社は人を選ぶだけでなく、選ばれる側でもあります。
求職者に「この会社で働いたら・・・」と「・・・」の部分を具体的にイメージさせることができれば、それは入社の決め手になります。
お仕事を探している方は、求人募集欄のどこをみるでしょう。
職種、給与、勤務地、勤務時間。
このあたりは必ず目を通すと思いますが、ハードデータだけではその会社で働いているイメージを持つことはできません。
そこで「アピールポイント」のような自由記載欄の活用です。
具体的に働くイメージを持ってもらう
アピールポイント欄や備考欄を必ず活用します。
そこに、「うちの会社はこんなに良いところがあるんですよ」と会社で働くことを具体的にイメージできるような内容を入れるのです。
よく目にするものに「キャリアアップイメージ」や「先輩からのコメント」などがあります。
これらも「こんな感じでステップアップできるのかぁ」、「こんな先輩と一緒に働くんだな」など、働くイメージを持ってもらうには有効な手段になります。
しかし、あくまでも自己評価です。
求職者から、「わたくしはパソコンのスキルが高いです」と言われるよりも、「MOS(マイクロソフト オフィス スペシャリスト)資格を持っています」と言われるほうがPCスキルのレベルが客観的に伝わります。
これと同じで、「うちの会社はこんなにいいところがあるんですよ」と主観評価をアピールするのも一つですが、他者からの客観的な評価のほうが有効なこともあります。
他者評価を入れるとは具体的にどいうこと?
他者評価とは、その会社が他から見て客観的にどのように評価されているかということです。
例えば取引先などの会社を対象としたアピール方法の一つに「ISO」があります。
これ対して子育て支援に積極的であることをアピールできる「くるみん」の取得や従業員の健康づくりに積極的に取り組んでいることをアピールできる「健康経営優良法人」の認定などは、客観的評価として、求職者へのアピール材料になります。
子どもを産み育てながらキャリア形成が可能な職場で働きたい、自分が将来父親になった時に子育てにも積極的にかかわりたい、長時間労働が当たり前のブラック企業には行きたくないなど。
給与や勤務地といったハード面だけではわからない、将来的に求職者が求めるライフキャリアにそった働きやすい職場環境かどうか。
そのあたりの判断材料を提供することができるということです。
福利厚生の中に、育児休業、短時間勤務制度などと書いていても、法律で定められた最低限の整備がされているだけで、実際に利用者はいないということも少なくありません。
例えば、育児休業や介護休業、年次有給休暇であれば、取得率。短時間勤務制度であれば、取得者数など、他社や全国平均と比較して優位になるポイントは、制度の列挙にとどまらず、具体的な数値を入れることも差別化の一つです。
そのような意味でも、「くるみん」などは男性の育児休業取得者がいるかどうか、女性の育児休業取得率が75%以上等の具体的な目標を達成している企業のみが認定されるため、客観的なアピール材料になるということです。(※「くるみん」「プラチナくるみん」は平成29年4月1日より新たに労働時間数についての基準が設けられます)
「健康経営優良法人認定制度」ってなんだろう?
特に優れた健康経営を実践している企業に対して、経済産業省がその善行や功績を表彰する制度をスタートさせました。
政府が過労死の問題にも本腰を入れての取り組みを始めている昨今、経営理念の設定・発信の取組や従業員の健康課題の把握状況、過重労働・生活習慣病の予防といった健康づくり対策などに積極的に取り組んでいる企業を認定するというものです。
先月、2月21日に初回の認定企業が発表されました。
「大規模法人部門(ホワイト500)」が235法人(当局管内:31法人)、「中小規模法人部門」が95法人(当局管内:17法人)とのことです。
中小企業法人部門には香川県の横田建設株式会社が認定されていました。
審査は、日本医師会や日本商工会議所はどが参加する「日本健康会議」が行っています。
2016年12月9日に応募は締め切られていますが、中小企業部門については、来年夏をめどに追加認定が行われるといいます。
ワーク・ライフ・バランスの推進、健康経営を経営戦略と捉えて取り組む
業務の効率化、生産性の向上、多能工化による休暇を取得しやすい環境の整備など。
これらは、労働人口が激減するこれからの時代、人材獲得や定着のために欠かせないポイントとなります。
ただ、漠然と取り組むのではなく、行政の認定制度の取得を目標とすることで、取り組みのための推進力が高まります。
そして、求職者獲得のためにもインパクトのあるアピール材料となります。
香川県の「くるみん」認定企業数は2017年3月1日現在で30社です。
始まったばかりの「健康経営優良法人」の認定企業は1社です。
大手企業はすでに取得していない企業の方が少ないかもしれませんが、香川県ではまだまだブルーオーシャン。
取得が当たり前のレッドオーシャンになる前に、動き始めるなら今です。
認定取得までの取り組みのネック等、取得を諦めてしまう前にお困りのことがございましたら、一度ご相談いただければと思います。