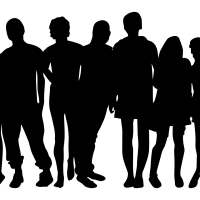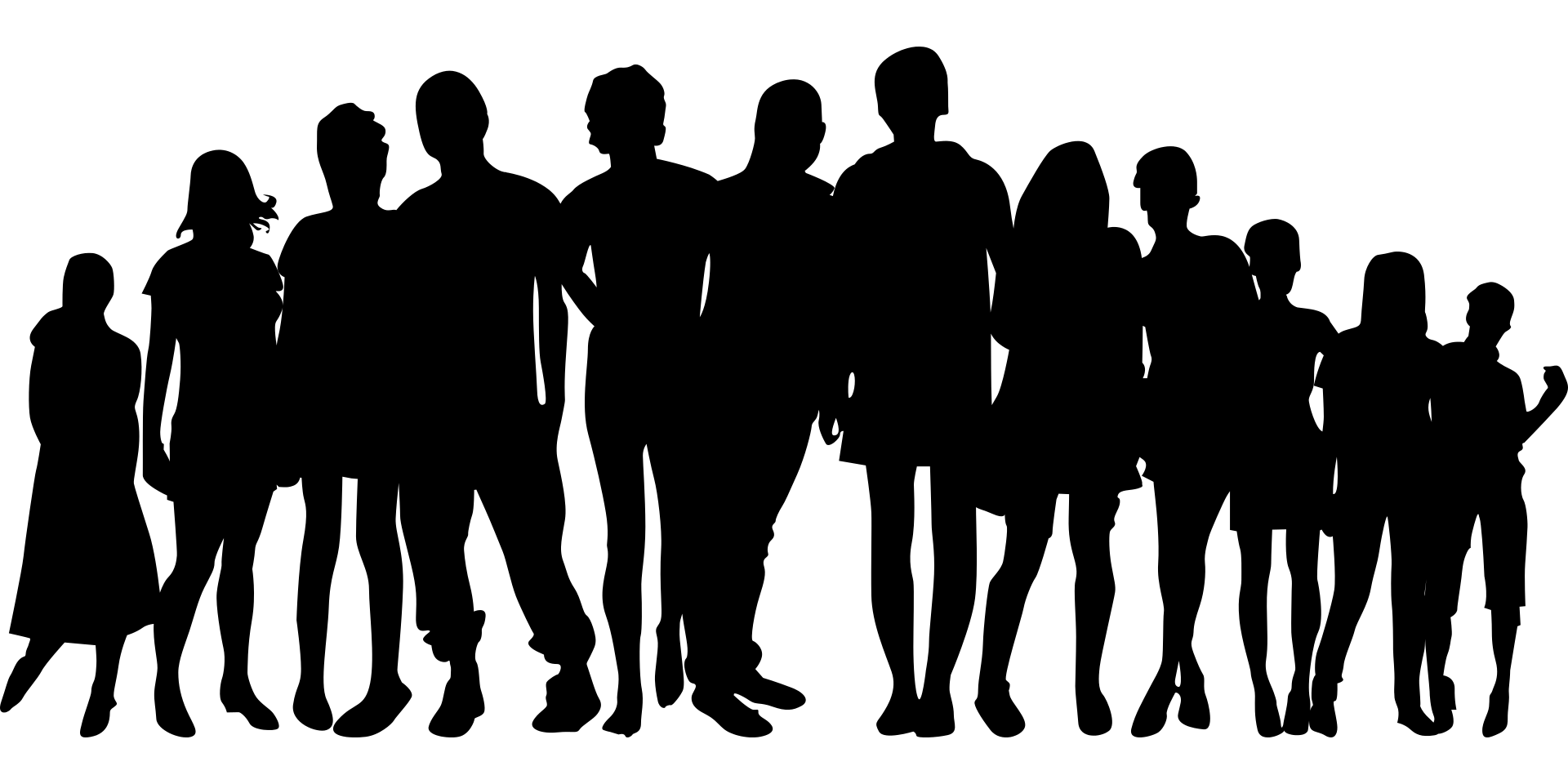少し前の話になりますが、アメリカのトランプ大統領がイスラム教7か国からの入国を一時的に禁止しました。
そのことに対して、AppleやGoogleなどの名だたるIT企業が入国制裁措置に抗議の声をあげました。
私自身、「ダイバーシティー」(多様性、幅広く異質なものが存在すること)という言葉は確かによく耳にするようになりましたが、具体的な分かりやすい効果を体感することは多くありません。
何となくいろんな考え方を持った人が集まることで、化学反応が起こることは理解できるような気がします。
ワークショップや小集団活動の中でも、異なる視点が入ることでの効果は実感値としてあり、頭では理解はしていました。
このニュースは、現在受けているIT技術の恩恵をはじめとして、これまでのIT技術の革新を支えていたのは「ダイバーシティー」だったのか…と改めて痛感する機会になりました。
「なるほど~そうだったのか!」と個人的に、今までの自分の体験を心にドスンと落としてくれました。
目次
パワハラが起きる背景
日本でもダイバーシティー(多様性、幅広く異質なものが存在すること)という言葉を耳にする機会が少しずつ増えているように思いますが、年間100を超える事業場をご訪問をして、企業訪問をしてこの言葉を聞いたのはわずか2社です。
パワーハラスメントが起きる背景の一つは、「多様性」だと言われています。
ここ20年間で非正規社員と呼ばれる方の割合は2割から4割に上昇しました。非正規社員とひとくくりにされますが、その中には契約社員やパート社員、アルバイト社員、定年退職後の嘱託社員、派遣社員など、様々な雇用形態が存在します。
社員の大多数が正社員と呼ばれる社員で構成され、中途社員より新卒で入社したプロパー社員が圧倒的に多かった時代は、「これはこういうもの」という規範が言葉を尽くさなくとも通じていました。
しかし、今は違います。
様々なバックボーンを持った人が集まる中で、「言わなくてもそのくらいわかるだろ」という感覚は通用しなくなっています。
20年前から現在にワープでもすれはその環境の変化を強く感じることができますが、長い年月を経て変化してきた職場環境の中に身を置いていると、その変化を大きなものを感じることなく、同じような指導を続けていることになります。
言葉を尽くす指導
昔は、「俺についてこい!」とか、「背中を見て育つんだ!」とか、口であれこれ説明せずに「見て覚えろ!」というスタンスの指導が成立していました。
企業内研修の中で、「コーチング的かかわり」や「Iメッセージ、Youメッセージ」、「フィードバック方法」についてお伝えすると、「昔はそんな指導必要なかったのにね。面倒くさい。」そんな心の声が見え隠れすることもあります。
しかし、「昔」と「今」とでは時代背景が大きく違います。
プロパー入社で、先輩と同じ道を同じように歩いてくことができる時代であれば、「俺についてこい!」が通用したかもしれません。
先輩がやっている姿を見て学ぶ時間が今より格段に多かった時代は、「背中を見て育つ」ことも可能でした。
「見て覚える」もなにも、今のやり取りの多くはメールで行われています。
昔はお客さんとのやり取りは直接会って話をする機会も多く、電話やFAXが主流で、どうやってやり取りしているのかを見て、聞いて学ぶ機会がたくさんありました。
上司への報告や連絡、相談も先輩や同僚がしている姿を直接見る機会がたくさんありました。
しかし今はどうでしょう。
仕事のやりとりはメールのCCやBCCで関係者にも共有します。社内でも直接的なやり取りを目の当たりにする機会は「昔」と比べると随分減っているのです。
「自分の時はこうだった」というその時とは、環境が大きく違うことを改めて認識した上でマネジメントをする必要があります。
来月から新入社員を迎える企業にお勤めの方、中途採用で様々なバックボーンを持つ方を迎える企業の方は、これら時代背景の違いを常に意識し、言葉を尽くして指導するということを心掛けてみませんか。
お互いのモヤモヤ、イライラが少し緩和されるはずです。