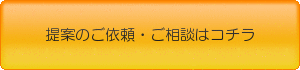勤務間インターバル制度の導入に踏み切ることを決定した企業が続々と増えているようです。
以前、出張日の睡眠確保として勤務間インターバル制度を導入という記事の中で「勤務間インターバル制度」について触れました。
目次
改めて「勤務間インターバル制度」とは
「勤務間インターバル制度」とは、勤務の終了から翌日の勤務開始までの時間に一定の休息時間を設けようというものです。
近年過重労働に注目が集まっていますが、導入すれば従業員の心身の負担を軽減することが期待されます。
休業状態にないまでも、心身の疲労により生産性が低いままに働いている従業員が多いことによる経営損失は、既にあえて言及するまでもないことかもしれません。
因みに、ここ最近の一週間のうち「体も心もスッキリ!」パフォーマンス80%以上でお仕事できた日は何日ありましたか?
その回答が直接生産性に関係しています。
なぜインターバル制度?何時間確保すればよい?
「業務起因性」・・・業務と発症との関連性が高いと判断され、労災認定に直結するケースが高まる時間外労働の時間数は1か月あたりおおむね80時間超です。
つまりこれが「過労死ライン」と呼ばれる時間数です。
1か月に80時間を超える時間外労働をしているということは、1か月をざっくり4週とすると、1週間に20時間の残業をするペースになります。
完全週休二日制で1週間が5日とすれば、1日4時間の時間外労働をしているという計算です。
1日当たりの法定労働時間は8時間、休憩時間を1時間とした場合、これらと合わせると、1日の拘束時間は13時間ということになります。
1日24時間ー拘束時間13時間=休息時間11時間。
休息時間11時間と言っても、そこから往復の通勤時間、食事の時間、お風呂などの時間、家庭時間などを引けば睡眠時間は何時間確保できるでしょうか。
たまに、「建設業などで肉体を酷使しているわけではないので、労働の負荷は低い。だから残業時間が多くても体に負荷はかかってない。」といったことを言われることがあります。
「過労死」で問題になっているのは、「睡眠時間」が十分に確保できないことによる心身の疲労です。
インターバルを何時間取ればよいかは、何時間くらい睡眠時間を確保できるかを考えると分からいやすいかもしれません。
ヨーロッパでは24年も前から導入済み
EU(ヨーロッパ連合)加盟国では、今から24年も前の1993年に「24時間につき最低連続11時間の休息時間」を確保することが、EU労働時間指令によって定められ義務化されています。
例えば、残業で午後11時まで働いたとしましょう。
翌日の勤務開始は8時からだとしても、11時間のインターバルをとることが必要となるため、出社は午前10時でよいということになります。
8時から11時までの就労しなかった時間、2時間分の賃金の支払いは当然にあります。
日本では法制化とまではいかないまでも、勤務間インターバル制度導入に関する助成金の申請受付が始まっています。
勤務間インターバル制度の導入に名乗りを挙げている企業
日本では、KDDIやNECといった情報通信業、IT業で導入が進んでいます。
電機大手シャープや旅行大手JTBグループの「JTB首都圏」も導入。
エステ業界最大手のTBCグループもインターバル規制を盛り込んだ労働協約を労組と締結。
以前記事にした、ケーブルネットテレビ局専用チャンネルの配信事業などを行っているジャパンケーブルキャスト株式会社(従業員数60人)。
「すき家」などを展開する(株)ゼンショーホールディングズも一部店舗で正社員に11時間の休息を確保できるよう、勤務間インターバル制度を導入する方針のようです。
え?何か問題起こしていなかった?と思った方。
そうです。同社は過去に深夜の時間帯に一人で店舗運営をする「ワンオペ」が問題視されたり、関連会社が違法動労時間の容疑で書類送検されたこととがありました。
しかし、3年前に社内に第三者委員会を設置し、働き方改革を進めています。
ニトリホールディングスも休息時間を10時間とする制度導入を合意しています。
一方、昨年の春闘でインターバル制度導入を合意した(株)サガミチェーンでは、いまだ実施時期が決まらない状況のようです。
業務に支障が出ると二の足を踏む経営者も多い
ただ、勤務間インターバル制度に関する助成金など、この制度が今ほど認知されていなかった頃の調査によると制度の導入率は2%です。
昨年から今年にかけて、次々と導入に名乗りを挙げる企業が多い一方で、業務に支障が出ると難色を示す経営者も少なくありません。
ただ、だからこそ導入に踏み切ることで、将来的な競争優位(人材の確保や定着等)に立てるのでしょう。
将来的に全てを機械やロボットでできる仕事であれば、職場環境の改善や整備など考える必要はないかもしれませんが、あなたの会社の事業はどうでしょうか。
制度を導入すればよいというものではないが、まずはやってみることが大切
単純に制度を導入すればよいというものではなく、実際運用していくためには、業務の多能工化やオペレーションの見直しなどが必要になります。
勤務間インターバル制度を導入することで、どのような課題が発生するのか、その課題にどのような改善策が考えられるか、頭の中だけでシミュレーションしていても時が過ぎ去るばかりです。
そして、その間にも労働人口の減少はとまりません。
多能工化一つとっても、今日はじめて明日出来るようになると考える人はおそらくおないでしょう。
勤務間インターバル制度の導入も試験運用期間などを設け、まず始めてみることが大切です。
大所帯でない、中小企業だからこそ、その規模を活かした導入ができます。