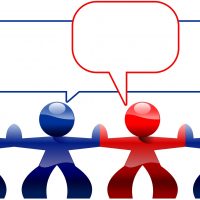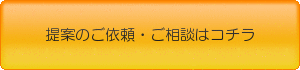あなたの会社には、育児休業や介護休業、または健康を害されて長期休職されている方はおられますか?
あなたもいつ病気になるとも限りません。
従業員の休業や休業者の復職に関しては、職場内にお互いさまの意識がいかに醸成されているかがカギとなります。
そして、お互い様の意識の醸成は、従業員間に勝手に意識が芽生えるものではありません。
事業者としての考え方、方針を明確にして発信をしていくことがまず初めにやるべきこととなります。
そんな面倒なこと必要ない?
本当にそうでしょうか。
目次
マタハラ防止措置の義務化
2017年1月からマタハラ防止措置が義務化されました。
事業者に義務付けられた内容は大きく4つ。
・妊娠出産等に関するハラスメントがあってはならない旨の方針などの明示
・相談窓口の設置他
・ハラスメントがおこったときの、迅速で適切な対応
・問題の起こった原因や背景となる要因の解消 など。
法律となった背景には、マタハラが世の中に横行しているという事実があります。
「育児休業はとってもいいけど、そのあとは辞めてね。」といったことを暗に示し、何の話し合いの機会も持たないまま、労働者本人は休業に入り、事業者は育休取得後は辞めるものと思っていて新しい人を採用しているということも今だにあるのが現実です。
「マタハラ」が起こる原因は?
なぜこのようなことが起こるのか?
その背景には代替要員の確保がうまくいかないという原因があるように思います。
男性が育休を取れない理由第1位は「代替要員がいない」ことだという記事が随分前に日経DUALに掲載されていました。
男性だけでなく女性ですら、まだまだマタハラを受けている人が多い理由は、休んでいる間、その人の仕事をどのように回していくのか、会社や管理職から何の指示もなく、「現場で勝手にやっておいて」という組織が少なくないという現実があるからです。
これは、出産に限らず、今後の団塊世代が75歳を迎えるまでに顕在化する親の介護や、ますます進む高齢化から自分自身の病気と仕事の両立、そして、メンタルヘルス不調者の長期休業など、全てに当てはまることです。
これから労働人口は確実に減少します。
今いる従業員にいかに継続勤務をしてもらうかを考えていかなければ、経営が成り立たない時代がくるのです。
もし、長期休業は困るから辞めてもらっている、辞めてもらうような方向に話を持っていっているという会社があったら、その考えを改めないと手遅れになってしまうかもしれません。
休業者の代替要員を確保するには?
では、具体的にどのように代替要員を確保すれば良いのでしょうか。
その方法を4つ紹介したいと思います。
1)ドミノ人事
休職者の代替者として、そのポストに一時的に部下を昇格させる仕組みとしてドミノ人事があります。昇格した部下は、一定期間上位の仕事にチャレンジすることになり、成長スピードが高まります。部下のさらに下位の者もその期間は昇格し、最終的な定型業務はアウトソーシングするか、派遣などで対応する。人材育成策としても有効です。
→「代替要員確保」というと、その人の仕事をそっくりそのまま同じようにしてもらう人を新たに短期間雇うことをイメージする事業場が多いです。
代替要員の確保についてお話すると、「休んでいる期間だけその人の仕事をかわりにやってくれる人なんていない」、「スポットでの求人は難しい。」と言われることがほとんどです。
休業に入る人の仕事を丸ごと出来る人を、しかも短期で雇うのは現実的ではないかもしれません。
仮に育児休業であれば、その人が休業に入るまでに「ドミノ人事」を実現する準備時間は十分にあります。
この方法は、ほかの役割のことを短期間でも体験することで、お互いに助け合う気持ちが強く醸成され、元に戻ってからの業務がスムーズーになるだけでなく、必然的に多能工化も進みます。
2)休業者の仕事を報酬付きで他に割り振る
休業者の業務を同じ部署、もしくは他部署からの応援で分担する場合、応援者への対価として、休職者の給与分を上乗せする方法があります。休業中の休業者は無休であるため新たなコストにはならず、応援者も無期われることになり、当事者にストレスのない方法です。
→手当として支払うと残業代にもその分を反映させなければならなくなるため、注意が必要です。一時金な慰労金としての分配がベストです。
時間外労働を削減するための取り組みとして、時間外労働の削減目標達成率をチームで競い、削減分の人件費を賞与で還元するなどの方法をとっている事業場もありますが、頑張りに対してインセンティブを与える方法は有効です。
3)OB・OGを活用する
自社をいったん退職したOB・OGを登録しておき、代替要員として活用します。
→会社で広報誌などを発行されている事業場は、その広報誌をOB・OGにも郵送するなどして、会社の状況を定期的にお知らせしておくなどしておくと求人を出した時の反応が違います。
4)多能工化、多職能化
従業員が複数の業務に着けるように、日ごろからトレーニングを進めておくと、代替要員へのシフトや兼務が容易になります。通常から職務分担票を作成し、パーツ化や平準化を進めることで、業務の俗人化を防ぐことが重要です。
→多能工化は事業者側のリスクマネジメントの観点からみても、非常に重要です。
多能工化は今日から取り組み始めて、明日出来るようになるものではありません。先日伺った情報システム会社では5年前の内部統制をきっかけに、チームで仕事を担当することに取り組み始めたそうです。
まだまだ専門性が高い分野で完全に多能工化でいないところもあるとのことでしたが、確実に時間外労働は減ったといいます。
他の事業場でも多能工化が形になるまで10年。月に100時間を超える残業をしている者がいるのが当たり前だった時代から、今では繁忙期であっても36協定の範囲内の45時間を超えることは滅多にないといいます。
「多能工化」のお話をすると「難しい」と一言で返されることも少なくないのですが、今着手しないと、大介護時代を迎える前に経営が成り立たなくなるかもしれません。
何もかもは一度にはできません。
あなたの事業場では、何から着手しましょう。
業務効率化、多能工化、生産性向上等、お困りのことがございましたら、お気軽にお問合せいただければと思います。
御社の現状をヒアリングさせていただいたうえで、作業のパーツ化などから多能工化のお手伝いが出来れば幸いです。