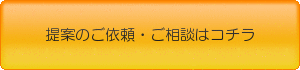先日、事務所を訪れた営業の方と名刺交換した際に、「健康経営って何ですか?」と聞かれました。
認定制度も始まったばかりでまだまだ香川県では(?)認知されていない「健康経営」。
経産省が始めた「健康経営優良法人」の認定制度は、優れた健康経営の取り組みをしている企業を顕彰するものです。
創設の目的は「従業員の健康管理を経営的支援から戦略的に実践する企業」として求職者や取引先企業、金融機関などから評価される環境を整えることとされています。
2017年2月末に発表された初回認定は、大規模法人部門で235法人、主張規模部門で95法人が認定されました。
今日は、この「健康経営」に中小企業が取り組むメリットを考えてみたいと思います。
目次
中小企業の健康経営優良法人。「認定基準」ってどんな項目があるの?
経産省が認定を始めたばかりの「健康経営優良法人」。
まずはその認定基準をみていきたいと思います。
因みに中小規模法人の定義は ①製造業その他:300人以下、②卸売業:100人以下、③小売業:50人以下、④医療法人・サービス業:100人以下の法人とされています。
■必須項目
(1)健康宣言の社内外への発信及び経営者自身の健診受診【経営者の自覚】
(2)健康づくり担当者の設置【組織体制整備】
(3)保健者との連携(求めに応じて40歳以上の従業員の健診データの提供)【評価・改善】
(4)従業員の健康管理に関連する法令について重大な違反をしていないこと(自己申告)【法令遵守・リスクマネジメント】
■選択項目
下記(A)「従業員の健康課題の把握と必要な対策の検討」のうち2項目以上
(A)定期健診受診率(実質100%)【健康課題の把握】
(A)受診勧奨の取り組み【健康課題の把握】
(A)ストレスチェックの実施【健康課題の把握】
(A)健康増進・過重労働防止に向けた具体的目標(計画)【対策の検討】
下記(B)「健康経営の実践に向けた基礎的な土台づくりとワークエンゲージメント」のうち少なくとも1項目以上
(B)管理職または一般社員に対する教育機会の設定【ヘルスリテラシーの向上】
(B)適切な働き方実現に向けた取り組み【ワークライフバランス】
(B)コミュニケーションの促進に向けた取り組み【職場の活性化】
下記(C)「従業員の心と身体の健康づくりに向けた具体的対策」のうち少なくとも3項目以上
(C)保健指導の実施又は特定保健指導実施機会の提供【保健指導】
(C)食生活の改善に向けた取り組み【健康増進・生活習慣病予防対策】
(C)運動機会の増進に向けた取り組み【健康増進・生活習慣病予防対策】
(C)受動喫煙対策【健康増進・生活習慣病予防対策】
(C)従業員の感染症予防に向けた取り組み【感染症予防対策】
(C)長時間労働者への対応に関する取り組み【過重労働対策】
(C)不調者への対応に関する取り組み【メンタルヘルス対策】
こんなにたくさんの項目クリアできない・・・
「あー、これね。これなら全部クリアできてます。」という会社は少ないと思います。
ただ、実際、事業場を訪問させていただくと、衛生委員会で話し合う内容がマンネリになっている、形骸化しているというお話を聞く機会が少なくありません。
なぜかというと、「衛生委員会」はやらなくてはいけないものであり、「衛生委員会」を月に1回開催することがゴール(目的)になってしまっているからです。
本来の「衛生委員会」を開く目的、そのゴールをどのように設定するかによって、話し合う内容は定まってきます。
例えば、50人以上の規模の事業場であれば、新たに「健康づくり担当者」を任命するのではなく、既存の衛生委員会や衛生管理者を中心とし、「健康経営」をゴールとしてみてはいかがでしょうか。
議題に困ることもありません。
次回認定を狙って上記の必須項目や認定項目を盛り込み、年間計画を立てて取り組みを始めるのもよいでしょう。
人材不足が深刻化しつつある今だからこそ
あなたがお勤めの会社では、人不足は深刻化していませんか?
帝国データバックが今年1月に実施した「人手不足に関する企業の動向調査」によると、正社員が不足している企業割合は前年度調査比6.0ポイント増の43.9%に達し、過去10年で最も高くなっています。
また、日本商工会議所が昨年6月に中小企業に実施した調査でも、「人員が不足している」企業は前年調査比5.3ポイント増の55.6%に上ります。
「今、うちは求人を出しても反応があるし、困ってないよ、大丈夫。」というところも、「あれ?おかしいな。反応がない…」という日がある日突然訪れます。
大企業よりも人員の確保が難しい中小企業だからこそ、新たな人の確保だけでなく、今いる社員にいかに長く勤めてもらうか、健康を維持し、生産性高く働いてもらう取り組みへの着手が急がれます。
「健康経営」への取り組みにより、疾病を理由とした休職や退職の防止、生産性の向上が図られるだけでなく、認定の取得や取り組みの内容や対外的にアピールすることで、求職者の反応は随分変わります。
ただ、その効果は、今日取り組みを始めて、明日出てくるものではありません。
「健康経営」への取り組みも業務の多能工化同様、取り組みをはじめてから効果が目に見えるようになるまでには、中長期的な視点が必要となります。
しかし、何もしなければ、5年後、そして団塊世代が一斉に75歳を迎える8年後の2025年には、その時気が付いても時すでに遅しという現実をだた受け入れるしかなるのです。
まず今、出来るところから始めてみませんか?
何からしたらよいかわからない、どうしたらよいかわからない、自分は取り組みたいと思うけれど、取締役社長が…などなど、まずは気軽にご相談ください。
現状の課題を言語化し、どのようなサポートが可能か助言ができるかと思います。
それを踏まえて、何をするのかしないのか、選択するのは御社です。