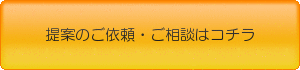あなたの会社の「相談窓口」は機能していますか?
相談窓口担当者が誰かご存知ですか?
実際に相談しようと思ったことはありますか?
目次
社内の「相談窓口」を設置するメリット
ここ数年、セクハラやマタハラ、パワハラやパート労働者などの社内の「相談窓口」の設置が事業場に法律で義務付けらるケースが増えています。
会社の経営者や人事労務担当者によっては、面倒なことが増えたとお考えの人も少なくないように思います。
だた、「相談窓口」を設置し、その窓口を機能させることで、様々な問題を水際で防止できることができるようになります。
あなたの会社、あなたがお勤めの会社にこんな問題はありませんか?
・採用しても人が育たない
・ハラスメントが原因と思われるきっかけで人が辞めている
・メンタルヘルス不調で休んでいた社員がいる、今現在休職中の社員がいる、退職した社員がいる
採用した人が辞めずに育っていたらか発生しなかったコストはいくらになっているでしょう?
人が辞めることにより発生した新たな採用コスト(求人募集費用のみならず、採用担当者が採用のために使った時間もコストです)はいくらかかったでしょう。
メンタルヘルス不調による休職者を一人抱えることにより、半年間でいくらのコストがかかったでしょう(年収600万円の社員が6カ月休職した場合のコストは422万円と内閣府は試算)。
パソコンを一台増やすのにいくらかかるなど、目に見える費用ではありません。そんな見過ごされているコストが山ほどあります。
それは、社内の「相談窓口」が設置さされるだけでなく、機能していれば発生しなかった費用かもしれません。
社内の「相談窓口」をいかに機能させるか?
人に相談することによって、気持ちが軽くなる経験を持つ人は少なくないのではないでしょうか。
職場の悩みについてはの相談先は、家族・友人へ相談した人が83.1%、上司・同僚が77.9%だと言います。
そして、実際に相談したことがある労働者のうち、ストレスが「解消された」とする労働者の割合は 31.1%、「解消されなかったが、気が楽になった」は 59.2%[同 56.2%]となっています。[厚生労働省:平成27年労働安全衛生調査(実態調査)より]
ストレスを抱えたまま、それに囚われる時間を少しでも減らすためには、「誰かに相談する」ことが重要な役割を果たしてくれるということです。
では、具体的な相談窓口の活性化方法をみていきましょう。
<事例1>
メンタルヘルスの相談窓口に「管理者用窓口」を設けた
相談窓口の設置当初は、従業員本人からの相談を受け付けていた。周知はしたものの、利用者があまり増えなかった。また、症状が出る前に相談してもらえれば早めの対処ができたのに…と悔やまれるケースも少なくなかった。
↓
「相談窓口」運営の目的として、予防的な観点からの相談活動も実施することを盛り込んだ。
↓
管理職用の窓口を設け、「管理者も部下のメンタルヘルスを確保するためにいつでも相談に来てほしい」と定期的に呼びかけた。
↓
相談窓口を活用してもらうポイントは「相談すること自体を前向きに捉えてもらうこと」
↓
「困ったことがあったらね」といったネガティブな印象を与えないよう、「従業員のための」「気づいたことがあったら」といったポジティブな意味合いの文章による訴求を図るなどの配慮をした。
<事例2>
派遣エンジニアを雇用する会社のハラスメントの相談スキーム
一次受付の段階では、健康推進課のスタッフが直接相談者の話を聞きながら解決を図っていく。
↓
相談者と十分に話し合い、事実や状況を精査
↓
【進め方を判断】
・ハラスメントの問題として進めて行くか
・本人から上司等へ相談することで解決できそうか
・一度カウンセリングなどを受けてもらって気持ちの整理をすることが必要か
↓
相談者が気持ちを整理していく過程で得られた、いまに上司等に対応していくのかの「気づき」によってスムーズに解決するケースも少なくない。
一方で、ハラスメントの問題として進めるべきと判断された事案は、厳正に対処する。配置転換も含めた職場環境の整備が必要となるケースもある。
本人と話し合った結果、「現在の状況や心情を派遣先に理解してもらおう」となった時は、本人の了承を得た上で、所属長・営業担当者と共有し、対応を協議する。
1)派遣先に改善を申し入れる(相手がお客様だからと遠慮するのではなく、自社のエンジニアのことを第一に考え、対等な関係として職場環境の整備を求めることになる)。
2)派遣先を変える
メンタルヘルスが低下して働けなくなったことで、会社に迷惑をかけたと自らを責めてしまうようなエンジニアもいる。
また、所属長や営業担当者も、エンジニアに対するケアだけなく、お客様との間に入った様々な調整が発生するため苦労も多い。
健康推進課のスタッフは、所属長や営業担当者の尽力を理解し、心情に寄り添いながら、エンジニアが活躍できるための休職や職場環境改善等の適切な対応がとれるよう提言している。
<事例3>
派遣先エンジニアに対する「メンタル相談」スキーム
■ルート1
派遣先の指揮命令者、人事担当者(チームで派遣されている場合のリーダー的な役割のもの)
↓
エンジニアの状況を日々把握し、体調が悪そうな場合には声かけ等を行う
■ルート2
「最近この人がちょっと心配だ」などの情報を派遣元に教えてもらう
↓
情報を受けた営業・技術担当者がエンジニア本人等と面談を実施し、状況を確認。
■ルート1または■ルート2より
↓
その場で解決を図ることが出来ない場合は、「従業員のためのメンタルヘルス相談シート」(本人了解のもと、具体的な不調の内容や勤怠の影響等の就業上の変化などを記入する)を所属長経由で確認。
↓
シートの内容を確認した健康推進課のスタッフは、様々な角度から見立てを行い、必要があれば本人とも話して、対処の方向性を判断。
・専門カウンセリングが必要なのか
・上司との話し合いが必要なのか
↓
それに基づいて必要な対等をとる。
↓
本人との間で、「何をどこまで誰に伝えていいのか」当の了承を得つつ、報告内容を固め、所属長経由で派遣先に提案していく。
うちには産業保健スタッフなんていない!
健康推進課などを設けている事業場は中小企業にはほとんどありません。
50人以上の規模の事業場であれば、衛生管理者にその役割を担ってもらうことも一つの方法です。
取り上げたエンジニアの事例は、一般的にエンジニアはメンタル不調にに陥れいやすいと言われ、加えて派遣の働き方が環境要因としてメンタルヘルスに影響する可能性が否めないという対応の難しい環境下での相談体制構築方法です。
よって、規模や業種業態問わず、応用、汎用しやすい事例と言えます。
「うちは、30人だから無理」、「体制整備もなにも私(代表取締役)が相談窓口だからそれでOK」と思考停止してしわずに、事例を参考に、相談体制構築までの自社の課題を明らかにしてみましょう。
そして、少人数で効果的に運営できるよう、管理者、人事担当者、相談窓口担当者(衛生管理者、産業保健スタッフ等)、小規模事業場であれば代表取締役のそれぞれの役割の分担と連携を考えてみてはいかがでしょうか。
社内の相談窓口体制構築、整備等、改善したい気持ちを是非ご相談ください。
お役に立てるアドバイスをさせていただけると思います。