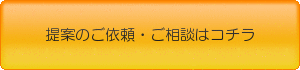働き方改革の一つに「ゆう活」があります。
「ゆう活」と言っても、香川県ではあまり認知されていません。
極一部の方が、「あー東京本社の一部の大手が何か取り組んでいるらしいね。」と認識されているくらいでしょうか。
一方で現状を打破するため、何かしらの働き方改革の必要性を感じている企業は香川県下でも少しずつ増加しています。
2年後の2019年4月施行を目指している労働基準法の改正(罰則付き時間外労働の上限規制)を見据え、総労働時間削減の準備を始めるためにも、この夏は「ゆう活」の導入を従業員の意識改革の第一歩にしてみませんか?
9月単月でもOK。他社を差をつけるためにも、今から着手すればまだ間に合います!
目次
「ゆう活」って何?
夏の生活スタイル変革の提案。「ゆう活」とは、日照時間が長い夏に、朝早い時間に仕事を始め、早めに仕事を終えることで、まだ明るい夕方の時間を有効に活用し、生活を豊かにしようという取組です。
詳しくは「ゆう活-始めよう!夕方を楽しく活かす働き方」(政府広報オンライン)を参照ください。
朝方勤務を導入することで、終業時間後に自己啓発をはじめとした自分時間を持つことや、家族団らんの時間、家事や子育て・介護、友人と過ごす時間などを生活を楽しむ時間を設け、仕事と生活のバランスをとり、豊かな人生を送ることを目的としたものです。
ダラダラと長時間会社にいても、集中できる時間は限られています。
しかし、長年の習慣というものはなかなか変えがたいもので、これだけの仕事量があるのだから、早帰りは無理と取り組む前から否定的なご担当者さまも少なくありません。
従業員の各々のタイムマネジメント能力を高めるためにも、健康経営の一環として従業員の生活習慣改善のためにも、応募者への自社の魅力付けの一つしても、「ゆう活」への取り組みは有効です。
各社の取り組み内容
では、具体的に各社どのような取り組みを行っているのでしょうか。
1)スタンダードな前倒し型
■6月から9月の期間に朝方勤務制度を導入。本部の社員(約100名)の勤務時間を30分前倒し、8時30分~17時30分として朝方勤務を実施。【小売業】
■5月から9月まで、始業時刻を1時間前倒し、勤務時間を7時30分~16時15分をして朝方勤務を実施。全従業員のうち、約90%が実施した。【製造業】
■夏季に、希望者を対象に出勤・退勤の時刻を1時間繰り上げる「朝方勤務」を導入。【不動産業】
↓
対象とする従業員の選定は三者三様です。
まずは本部の社員から始める企業、全従業員を対象とする企業、希望者を対象をする企業。各社の業態や社員の希望等に合わせて運用方法は異なりなります。
2)始業時間選択型
■通勤事情を考慮し、交通アクセスの良い3店舗を対象として、9月の1か月間実施。基本8時30分の始業時刻を最大7時30分まで繰り下げ可能とする。【金融業】
■間接部門は8時45分~17時45分の基本勤務時間のほか、複数の勤務時間帯から選択が可能な制度を導入。朝方勤務(7時から勤務開始可)も推奨。【航空業】
↓
時差出勤的なイメージで、始業時間を30分、または1時間単位で早めることが選択できるようにしています。従業員各々の事情に寄り添った導入方法です。
「ゆう活」賛成派と反対派の意見
マイナビニュース会員男女300人へのアンケート結果によると、賛成派は36.3%。反対派は63.7%となっています。
ゆう活をやってみたいと思った人は、定時退社をして食事や飲みに行ったり、スポーツやジム、習い事、買い物、家族との時間を過ごすなど「プライベートの充実」「自由時間の捻出」を思い描いていた。仕事も朝早くからスタートするため、「涼しいうちに活動できる」「能率がいい」「仕事に集中できる」というメリットを挙げる人もいた。通勤ラッシュを回避できる、早寝早起きで健康になるなど、別の面での良い効果を期待する声もあった。
「いいえ」と回答した人たちの多くは、「ゆう活」のアイディアを机上の空論、と考えている節がありそうだ。「早く仕事を始めたら勤務時間が長くなるだけ」「どうせ残業が待ってる」「勤務体系は変わらない」と、諦めムードが漂っていた。また「疲れる」「そんな元気がない」「家に帰って寝たい」など、ゆう活というよりは休息を望む声も多かった。
これは2016年8月12日の記事になりますが、昨年実際に導入した企業は、反対派の「早く仕事を始めたら勤務時間が長くなるだけ」という諦めムードを感じさせないような工夫を凝らしています。
運用を軌道に乗せるための工夫
導入している企業は、従業員に制度を上手に活用してもらえるよう、各社工夫を凝らしています。
▼ルールづくり
・取り組みやすくするため、前日の17時まで申請を可能としている。
・朝方勤務は間接部門を対象として導入したが、全社的に働き方見直しのための3つの社内ルールを設定。1)原則、終業時刻までの速やかな退社を促し、遅くとも19時までに退社 2)会議は17時30分まで 2)メールや電話の発信は平日18時30分まで
▼社内ルールの見直し
・早帰りする従業員を考慮し、夕方から所定時間外にかけて開催していた会議を朝へシフトした。
・「ゆう活」期間中は、17時25分以降の部門間・店舗間の電話連絡を控えるルールを徹底した。
・8時45時までは「集中タイム」と称し、上司方部下に話しかけることを禁止した。
▼意識の醸成
・「ゆう活」適用者が退社しやすい雰囲気をつくるため、「朝方勤務適用者カード」を作成し、周囲に知らせている。
・ホワイトボードやスケジューラーなどを活用し、始業時刻や終業時刻等を表示するようにし、職場ごとでの朝方勤務利用に関する意思表示を見える化した。
・終業後の時間活用について、健康増進支援(運動による心身への効果の情報提供・アロママッサージセミナーの開催)や子育て支援(知ると子育てが楽しくなる家庭学級の開催)や能力開発支援(生産革新リーダーシップ、コミュニケーション力、自己研鑽用水晶図書紹介)等、支援策の提供した。
▼業務改善
・社員の出勤、退勤時刻の現状を把握した上で、会議の運営方法、資料の簡素化、ルーティン業務の整理、処理方法の見直しを実施した。
・若手社員について、中堅社員が仕事の優先度や求められる仕事の完成度についてあらかじめ指示するなど「業務の交通整理」を指導した。
▼評価に反映
・朝方勤務等働き方改革で短縮した勤務時間を支店の業績評価へ反映した。
・早出残業の割増率を30%(終業時刻後は25%)に改定した。
ただ「早く来て早く帰りましょう!」と号令をかけるだけでは、本来の目的は伝わらず、いづれ形骸化してしまいます。
始業時間は前倒ししたものの、退社時間は変わらず、勤務時間が伸びてしまうのでは本末転倒です。
制度の導入と併せて、働き方の見直しに関する社内ルールを整備し、業務の多能工化や平準化をいかに進めていくかが重要です。
「ゆう活」取り組みの効果
▼残業時間減少
・本社の時間外労働時間が前年度同期比で約2割減少した。
▼従業員満足度の向上
・社員から「朝集中して仕事ができた」「夕方に家族団らんができた」「ゆう活を実施しない社員の時間管理意識が高まった」等好評であった。
・アンケートを実施したところ「子どもの送迎が楽になった」、「夕方に自分の時間が確保できるようになった」とワーク・ライフ・バランスの実現に効果があるため、10月以降も通年で取組を行うことを決定した。
▼意識改革
・「朝、集中して効率よく仕事ができる」など、働き方の見直しが好評であり、業務効率化を図りながら、今後もワーク・ライフ・バランスの実現のための取り組みとして実施する予定。
▼対外的イメージの向上
・従業員から「取組期間を長くして欲しい」という希望が寄せられ、好評である。ワーク・ライフ・バランスに取り組む企業であるということで、対外的に企業イメージが向上した。
参考:ゆう活取り組み企業一覧
「ゆう活」導入のデメリットは?
「ゆう活」導入の工夫やメリットをみていきましたが、実際運用するうえでデメリットとなることは何でしょうか。
まずは、会議の開催時間一つとっても、今までのやり方のままでは難しくなることが出てくるため、その調整作業が必要となります。
「そんなものだ。それで良い。」と思っていたことを変えなければならない時、人には抵抗感が生まれます。
そこをどのように工夫して個々の意識改革から組織の意識改革に繋げていくかカギとなります。
ほんの少しの意識改革から従業員一人一人が少しでもメリットを感じてくれれば、その後の運用に拍車がかかります。
次に、仕事内容により一部のものしか導入できないことが不公平感を生む、不公平である。というものがあります。
実際、仕事の内容が異なるため、皆が同じ必要があるのかが疑問ですが、皆が同じことが公平であるという固着的な考え方が蔓延している場合、一部に導入などありえないという意識が生まれてしまいます。
ただ、これらのデメリットは、「ゆう活」だけの導入で何とかしようと考えるのではなく、その他の「働き方改革」と合わせた運用上の工夫を凝らすことによって、解消されるものです。
次年度の本格導入に向けて、まずは単月でも運用をはじめてみませんか?